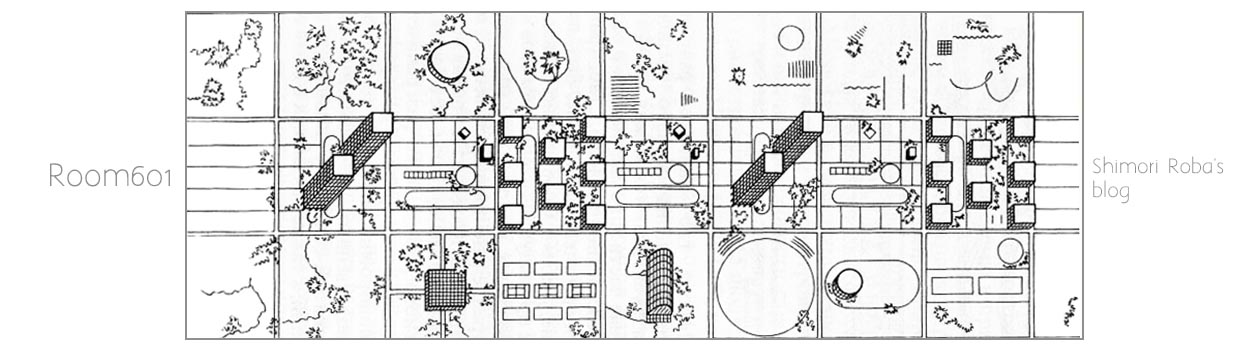昔、廃虚が好きでした。
いわゆる廃虚マニアです。
日本でいちばん行きたい場所は軍艦島、といつも言っていました。
それが変わったのは、ほかならぬ軍艦島とやはり長崎の池島に行ってからです。
このふたつは元炭鉱です。
そこに人が生きていたこと。
廃虚になるには、産業の衰退やそれ以外のいろいろな事情があることに
思い至りました。
なのでそれ以降は、廃虚には理由がある。
その理由を知らないと行く意味がないな、と考えるようになりました。
そこに住んだひとがいて、捨てられた意味がある、
と気づいてから、廃虚が好き、なんてかんたんに言えなくなりました。
チェルノブイリのゾーンと言われる場所に入れるようになって
最初は限られた研究者やジャーナリスト向けのツアーが入り、
いまは、数社の旅行会社が参画して望めば誰でも行けるようになっています。
ゾーンを舞台にしたゲームがあり、そのマニアのひと、
廃虚マニアのひと、
そしてわたしのようにチェルノブイリだから行ってみたいというひとが
年間に約5万人訪れるそうです。
ここやアウシュビッツ、日本だと水俣・福島などを
訪れることをダークツーリズムというんですね。
評論家の方がやっているフクシマを観光地化にする試み等、
わたしはまったく否定しないですが、
なんだかちょっと不得意な言葉です。
カテゴライズされるのがなんであれ苦手だからでしょうか。
ダーク、という強制力も苦手、観光と嘯くのも苦手。
自意識過剰なんだと思います。
でも行けるものならやはり行かなければ、ということで、
ツアーに参加して行ってまいりました。
ゲートを入り、犠牲になった方のモニュメント、
廃虚化した幼稚園、
金属のドームで覆われた4号機、
いまも線量が高いという赤い森、
そして、一日にして廃虚になった町プリピャチを回ります。
英語のツアーだったので、すべての言葉が理解できたとは
とても思えませんが、
丁寧なガイドさんで、
洗練され、整理されたツアーを体験しました。

これは入口のところにあるモニュメント。

ガイガーカウンターがレンタルできます。

これは幼稚園の庭に落ちていた人形。
こういったことは、ほとんどの場合、
後々のひとが演出で飾ったものらしいです。
そうですよね。
自然にこうはならない。
ひとは、罪深いなあ、と思います。
そうやって演出された空間で、
どこを撮っても絵になる。そういう瞬間が多々ありました。

幼稚園の内部。と田島さん。
お昼ご飯はゾーン内のレストランで食べます。
ゾーンのなかでごはんを食べる。
もちろん安全なごはんですが、
その瞬間がいちばん、身体感覚が発動した気がします。
昔、ドイツのドキュメンタリだったように記憶していますが、
チェルノブイリを訪ねる記録があって、
ゾーンに戻ってきたひとたちをサマショールというのですが、
そのひとりを訪ね、出してくれた食事を規則だから、
という理由で逡巡の末食べないというシーンがありました。
出したおばあさんの悲しい瞳が焼き付きます。
いまよりずっと線量が高かった時代の話です。
そのイメージとか、
辺見庸さんの「もの食うひとびと」の鮮烈さとか故かもしれません。

これが4号炉。この銀色の覆いができたことで、
線量が劇的に減り、
ツアー客が増えたのだそうです。
無人なカンジで撮れていますが、
ここにはすごくたくさんひとがいます。
そして幻想を抱いてほしくないのですが、
チェルノブイリの廃炉はまだまったく終わっていないのです。
覆っているだけ。
事故後もとなりの1号炉から3号炉までは、
発電を行っていました。
国際社会からの要請で、発電が止まったのは、2000年のことです。
ウクライナでは、
原子力に反対するひとたちのあいだでさえ
過渡期的には原子力使用がリアル、という考えがあるようです。

そして廃虚の街、プリピャチです。
これはとても賑わっていたカフェ。
食券を売る自販機の前で説明してくれるガイドさん。

常にその場所と過去の写真を対比しながら説明してくれます。

おそらく世界でいちばん有名な観覧車。
この遊園地は開業間近で、
稼働しないまま住民たちが避難しました。

市民センターのような場所の飛び込み台。
ここで練習していた子供たちが、
なにかの大会で賞を取った、
というようなことを言っていた気がします。


元小学校です。
ガスマスクがうずたかく積まれていることで有名です。
田島さんの後方に広がっているのがガスマスク。
この部屋もいろんな意味で演出されていましたが、
ガスマスクはじっさいにこの学校の残留物のようです。
原発対策というより、
核戦争対策だ、とのことでしたが、ほんとうなんでしょうか。
ペレストロイカ後とは言え、
まだまだ冷戦時代を引きずっていた時代の事故です。
いまのロシアの状況とはまた違う状況だったのだと思いますが、
小学校にこんなにも大量のガスマスク。
穏便とは、程遠い情景です。
ガイドさんの口から何度もソビエトシステム、という言葉が出ました。
ウクライナはいまは独立していますから、
ソビエト時代についていろいろな思いがあるのだと思いました。
言葉ができたらもっともっと話したいことがたくさんあったのに。
観光地化された、といわれるチェルノブイリですが、
わたしたちを案内してくれたガイドさんは、
プロフェッショナルとして、
いわゆる日本の観光ガイドとは一線を画する
きちんとした案内をしてくれました。

最後に行ったここは、ソビエト時代のレーダーだそうです。
写真ではわからないけど超巨大です。
あまりに巨大で実現化しないうちに事故が起こった、とのことですが、
いったいこれでソビエトはなにをやっていたのでしょうか。
軍事大国としてのソビエトに思いを馳せざるえない施設でした。
どこに行っても思うのですが、
感性が乏しいのか、
人生が変わるほどのショックというのは受けないです。
ああ。ここに。ほんとにあったんだなと。
チェルノブイリ事故は、ほんとにあったんだと。
ひとがいなくなった街を歩けば、
それは、悲しみのようなものには浸されます。
けれど、思った以上に淡々とわたしは歩きました。
悲しみを深くするのも違うし、
体温が上がるような興奮も違う、
カンタンに衝撃を受けたりするのもなんだかそぐわない。
すごく醒めていました。
無理にそうしたわけではなく、
そうなってしまう。
ショックなんて受けなくても、
ここに来たというだけでどうせ人生は変わってしまうのだから、
とにかく平熱で見ればいい、見るべきだ。
そう思い歩きました。
行けるんです。個人旅行でも。
もし必要なときは連絡ください。
行き方くらいは、教えられます。
それくらいしか、教えられないけれど。