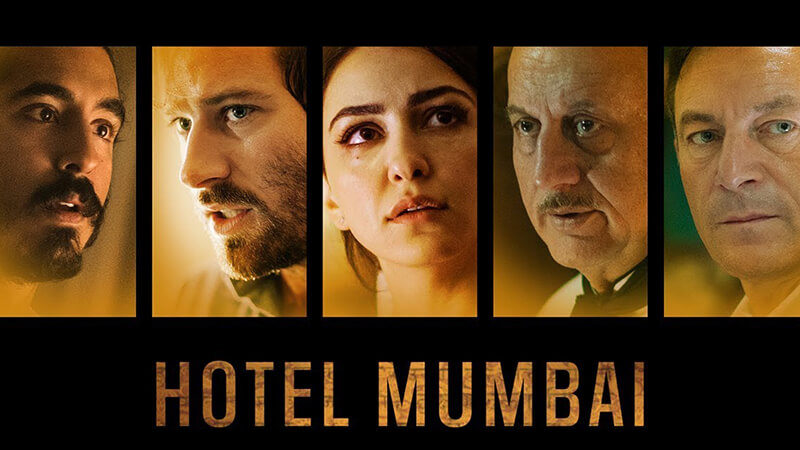今年もたくさん映画見た。
家の近所のシネコンが歩いていけるので、
レイトショーやってるしで、
大作系は主にそこで。
レイトショーは安いのでちょっと高級なホームシアター感覚。
稽古後でも行けるタイムスケジュールなのもありがたいですね。
わざわざ出かけて行くのは単館系です。
あいかわらずドキュメンタリ多しです。
今年は、
「僕達は希望という名の電車に乗った」と
「存在のない子供たち」
の2本が衝撃的で、
加えて邦画の「蜜蜂と遠雷」がとてもよくて、
ベスト3決まりだな、と思ってたら年末にキタ。
「ホテル・ムンバイ」
監督は、これが長編一本目というオーストラリアの監督。
アンソニー・マラスさん。
テロとそこからの生還というハードな題材ながら、
奇跡の実話、とあるので、それ系くらいのつもりでいくと、
わたしみたいな怖がりは、
しょうじき死にます。
わたしたちは劇場で、リアルなテロに遭遇するハメになるのです。
怖がりなのに、
こういう映画はどうしても行ってしまうわたしなので、
そこそこ数は見ていると思うんですが、
そのなかでもリアリティと緊迫感が、
群を抜いていました。
しかし、ファーストカットからすべてが素晴らしいので、
怖いけど出られない、
これは傑作だからぜったい最後まで観なくちゃいけない、
悲壮な決意でがんばって、
ほんとにがんばって最後まで観ました。
エンドロールでは足が震え、息が切れてました。
ISテロを描いたものはドキュメンタリなんかも観てますが、
なぜそれが起こるのか、
なかなか腑に落ちないところはありますよね。
もちろん無差別テロは許されざることなんですが、
彼らの憎悪の源となった米ソの冷戦、
グローバル経済の歪み、
さらには石油の利権、
そこに相いれない宗教の問題が絡み合います。
常に世界の矛盾の吹き溜まりにされてきた中東のストレスが、
噴き出したのが、イスラム国。いわゆるISです。
もちろんIS自体は歪んだ思想、
イスラム教の間違った引用ではあるんですが、
トップシーンから、その大きな枠組みがしっかり提示され、
物語が始まります。
もうすでに悪の根源がどこにあるのかもわからない状態のなか、
テロの火ぶたは切って落とされる。
テロが始まる瞬間は見事です。
たくさんの人が集まる駅で、
とても滑らかにテロは開始する。
いつわたしたちが、この場所に立ち会うことになっても
おかしくない。
それを一瞬でわからせてくれる。
そして。
これほど緊迫感のある内容なのに、
後味としては、ヒューマニスティックで
あたたかな気持ちが残る、というのが、
この映画の神がかっているところだと思います。
しかもそれはカンタンに成し遂げられているのではなく、
ちゃんと哲学に乗っ取った脚本が、
ご都合主義にならないギリギリの断片で
その瞬間を切り取り、
そのレイヤーを重ねていくことで成し遂げられています。
俳優がすべて素晴らしく、
実行犯のテロリストにまで目配りがきき、
それに俳優も応えている。
究極の状況のなかで、
たくさんの人々の愛と努力が丁寧に描かれ、
それがこの得難い後味となって結実しています。
監督の言葉。
「互いを受け入れること、教育、様々な文化を理解することが、安全な世界を築いていくために不可欠だと証明した。この映画が、それらすべてをうまく伝えていることを願っている」
(アンソニー・マラス監督談)
この監督の精神が徹底され、
それは、わたしの文化、わたしの精神も
大切にしてもらっているという感覚を見ている間中、
伝え続けてくれます。
ひととひとの断絶の最北に位置するとも言えるテロ。
その唯一の解決方法。
同じ場所に存在させた奇跡のような映画でした。